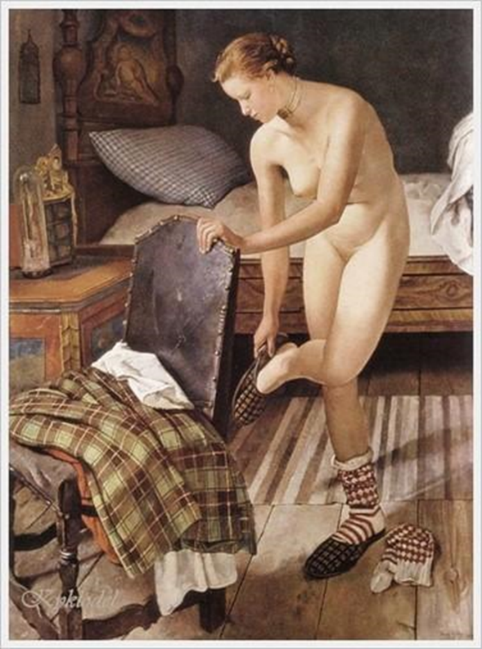みやの ひろ
得てして、職業紹介本はお堅いイメージがある。特に医療系の職業となればなおさらだろう。
本書の依頼がきたとき、従来のイメージを払拭した、手に取りやすく読みやすい本を書くことが私に課せられた命題だと勝手に考えた。
幸いにも、編集者から提示された「言語聴覚士になろう!」というタイトルはポップで親しみやすい。このタイトルに合うように、内容面にもある程度の“遊び要素”を取り入れてやわらかさを出し、かつ、メリハリをつけることでストレスなく読み続けられるよう工夫を施すことを提案する。
「すてきなお考えですね。まずは自由に書いてください」
編集者からの理解も得られ、新しいイメージの職業紹介本の作成に取り掛かる。原稿を書いているうちに、多少、“遊び要素”の域を超えたおふざけの箇所も入ってしまったが、それはそれで一興だろう。
編集者がどんな反応をするのかワクワクしながら原稿を提出する。そして、数日後、編集部で遊び要素をほぼ削除した校正刷りが手元に届く。
……従来どおりのお堅い本になっとるやないかーーーーい! え? 原稿提出段階では面白いって言ってたよね? 個性的って言ってたよね? 自由に書いてくださいって台詞は嘘だったんかーーー!!!
まさかの全ボツ。最高にハイなスタンド使いも真っ青の無駄無駄ラッシュだ。なぜこうなったのか。よくよく編集者の台詞を思い出す。
「まずは自由に書いてください」。自由に書いていいと言っている。
「まずは自由に」。絶対に言っている。
「まずは」。まずは……!? そのまま採用するなんて一言も言ってない!
これは、まさか! 叙 述 ト リ ッ ク!
……してやられたーーー! まさか一編集者が高校生探偵でも見逃してしまいそうな高等技術を駆使してくるとは! さすが出版業界、レベルが高ぇぇぇぇ!!!
だが、こちらだって言葉のスペシャリストの異名をもつ職業。やられっぱなしで終わるわけにはいかない。編集者に気付かれないように、いや、むしろ編集者が賛辞を贈るようなトラップを仕組んでやろうじゃないか!
そう、それはまさに超高難度ミッション。二重三重に張りめぐらせた網の先に、ついに編集者からその言葉を引き出すことに成功する。
「このコラムのタイトル、とてもすてきですね」
……よっしゃーーー! してやったぜーーー! ついに、ついに編集者にバレることなくトラップを仕掛けることに成功したぜーーー!!!
というわけで、本書は遊び要素たっぷりでお送りしました。本書とは全く関係がない「原稿の余白に」でごめんなさい。
ちなみに遊び要素とは漫画や映画などのパロディーです。わかりやすいものもあれば、すっごく巧妙に隠しているものもあります。最低でも1章につき1つは埋め込んでいますのでぜひ探してみてください(この「原稿の余白に」にもいくつか埋め込んでいます)。
そういえば、この文章のタイトルは「答え合わせ」でしたね。ですが、トラップの経緯に一生懸命で答えを書く紙幅がなくなってしまいましたので自力で見つけてください。ちなみにヒントのひとつは海賊王です。では、答えの続きはウェブで。なんちて(笑)。