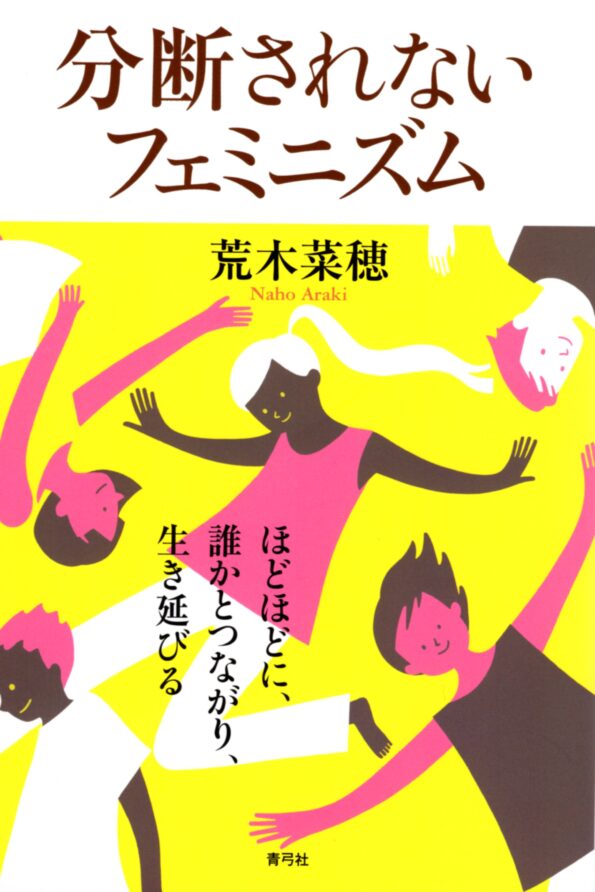石井達朗
現在の舞踊を中心にして、パフォーミングアーツ全般に対するわたしの関心は、もとをたどれば、幼少期に1年に1度、母が連れていってくれたサーカスにある。大きな神社の境内に秋になると市が立ったのだが、それと並行して神社から少し離れた空き地にサーカス団がやってきてテント公演をするのが恒例だった。子どもにとっての娯楽がいまのようになかった時代、秋にやってきて、終わると跡形もなく消えていくサーカスは、異形の人たちがもたらす最高の楽しみだった。テントのなかに一歩足を踏み入れると、馬糞のにおいとサーカス芸人たちのきらびやかなスパンコールが同居している。どこにもない不思議な世界。とくに魅せられたのは曲馬と空中ブランコである。大人になってからは、欧米はもとより中国、韓国、インドなどの町や村でさまざまなサーカスを観てきた。
綱渡りに引かれるようになったのは、サーカスという集団を離れて、野外の高所でパフォーマンスをおこなう人たちがいるからである。彼ら/彼女らは孤高の存在だ。文字どおりの独立独歩の冒険者たちである。サーカスのように鳴り物入りで綱渡りを盛り上げてくれるわけではない。何よりも高所綱渡り師たちは、サーカスでアクロバットするほかの芸人たちとはどこかちがう。最近のサーカスは、わたしの子どものころとは比較にならないくらいの大きな鉄骨に支えられたテントを使うので、テントのなかではるかてっぺんを見上げるようにして綱渡りを観たという人も少なからずいるはずである。その場合は、落下防止のネットが設置されていたり、綱渡り師とワイヤーを結ぶ「テザー」とか「ハーネス」を装着したりするなどの安全対策をとっている。
それにしても高所綱渡り師たちとは一体、何者なのか。歴史をみると、一瞬の油断で、あるいは何らかの物理的な条件が不備であったために命を落とした者たちが少なくない。大けががもとで残りの人生を車椅子などで生活した者たちはもっと多いだろう。しかし、彼ら/彼女らは決して向こう見ずの命知らずではない。なぜあえてそれほどの高所に挑戦するのか。
そんなふうにわたしに迫ってきたのが、フィリップ・プティである。彼の生のパフォーマンスを1度だけ、1980年代末のニューヨークで観たことがある。プティといえば、74年に、110階建て、地上410メートルを超えるニューヨークのワールドトレードセンタービル2棟の屋上に長さ42メートルのワイヤーを設置して、命綱なしに渡ったという歴史的な行為がある。すべて違法であることを承知のうえでおこなった確信犯である。プティの助っ人たちは、徹夜で超高層ビルの屋上をワイヤーでつなぐという大仕事をしたのだ。プティも一睡もせずにこの作業をやったあと、その日の朝、綱渡りを決行した。「勇気」や「挑戦」などという言葉さえ色褪せて聞こえるほど、度を超している。
歴史をひもとくと、驚くことにフィリップ・プティに勝るとも劣らない高所綱渡り師たちが少なからず存在してきた。これは決して男たちだけではない。女たちもいる。そういう人たちに言葉をとおしてできるだけ肉薄してみたいと思ったのが、本書を書き始めたきっかけである。高所綱渡り師について語る場合、数字が物を言う。いつ、何歳のときに、ロープの高さ、長さ、太さ、バランス棒の長さ、集まった群衆の数は……など。そのほか、ロープの下に設置する安全ネットの有無、ハーネスなどの墜落防止対策をしていたかどうか、天候はどうだったか、ロープの種類は麻か鋼か、など。不幸にも墜落してしまったのなら、その人は亡くなったのか。墜落した理由はどこにあるのか。墜落はしたけれど命拾いしたのなら、その後の人生はどうだったのか。わたしの好奇心がふくらめばふくらむほど、数字による具体的な記述も増えてくる。20世紀前半から19世紀へと時代をさかのぼるほど資料が少なくなったり、資料によって記述が異なっていたりと、困惑させられることもよくあった。
高所綱渡りをする者たちについて知りたい情報は尽きないが、わたしにとって最大の疑問は、彼ら/彼女らは一瞬にして命を失ったり、残りの人生を障がい者として生きなければならなくなったりするかもしれないのに、なぜ綱を渡るのかということだ。彼らは精神も肉体もわれわれ常人とはちがう何かをもっているのか。それともさしてちがわない人たちなのか。恐怖、不安、躊躇をどんなふうに克服できるのか……など、尽きることがない問いが追い立てるように執筆中のわたしを突き動かした。それらの問いに対する答えはいまだに一筋縄では捉えられない。
本書を書き終わってひとつ感じていることがある。人という生き物は自分が想像する以上に、途方もない可能性をもっているにちがいないということだ。外に羽ばたこうとウズウズする心身の力を内包している。それが、最近はケータイやパソコンなどのデジタルテクノロジーによって、いつも押し込められているように思えてしかたがない。高所綱渡り師という静かな挑戦者たちが、歴史のなかにいつも存在してきた。そして現在もいることに思いを馳せてみたい。そのことが、いまや当たり前のようにITの森の住人になってしまっている我々に、何か根底からちがう尺度を与えてくれるかもしれないと思うのだ。
『高所綱渡り師たち』試し読み