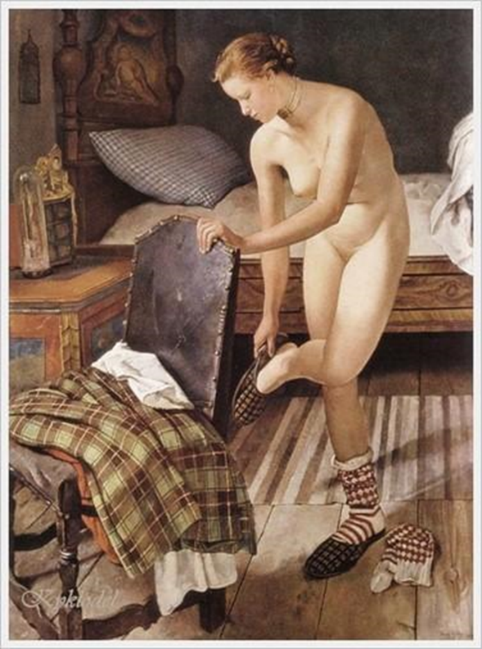永吉雅夫
この年齢になって、ようやく単著を一冊まとめた。それが本書である。かなりの原稿量になっていることはわかっていたが、500ページを超えるものになろうとは思いもよらなかった。しかし、いわば古参の初陣としては、それぐらいでかえって見苦しくなかったのではないかと、いまは思っている。
刊行後のよしなしごとのあれこれを記してみよう。
ちょうど、定年退職を1年前倒しして2020年度末での退職を伝えた時期でもあったのでいい区切りの一冊にはなったが、わたしに退職記念という意識はそもそもない。しかし、知人たちは、なるほど退職するんだと受け止め、そのように言ってくる人もあったので、いやいや、そうではありません、これを最初の一歩としてこれから……と応じると、ニコニコ顔であきれられた。
あきれるというと、出版した本が『「戦時昭和」の作家たち――芥川賞と十五年戦争』であることに多くの知人がオドロイタ、そのことに、かえってわたし自身が驚かされた。なにも、読んで拍案驚奇、一読三嘆というような話ではない。知友諸氏の多くが、わたしを近世の文学・芸能の徒と見なしていたらしく、その男の出版物なら、いまの関心からいけば石川五右衛門か歌舞伎を扱ったものにちがいないと思ったらしい。確かに、大学での担当科目ということで言えば、近世文学関係のシラバスが同僚諸氏の目には触れることが多かったのだ。それが、「戦時昭和」で「芥川賞」だったから、友人が面食らったというのも無理はない面はある。しかし、わたし自身はずっと日本文学近世・近代を守備範囲と決めて、そのように文章も書いてきたつもりだったから、諸氏のそうした反応にこちらが驚かされたのである。主観と客観のズレ、というと大仰にすぎるが、しかし、セルフ・イメージと第三者の眼というものはなかなか一致し難いものかもしれない。
それとは少しズレるが、まして、ご時世、自己の信念の前では第三者にどう見えるかなど塵、芥、そんなものにこだわるのは信念薄弱か、へたをすると単なる八方美人の風見鶏だと思われかねない。その結果、第三者の眼を仮構して自己を検証するという、オトナなら当然の自己省察までがスキップされてしまい、逆に確固たる自恃が疑われるような事態が出来しているのではないだろうか。
たとえば、「教養がじゃまをする」という言い回しを聞かなくなって久しい。こういうふうにすれば自分が得をする、有利になるということはわかりきっているのだが、そうであるからこそかえってそのように振る舞うのははばかられる、自分で許せない、そんなとき苦笑交じりに「教養がじゃまをして」とつぶやいて、結局、みずから自分の得や有利を取り逃がしてしまう。現在では絶滅危惧を通り越して絶滅、はっきりと死語になってしまったとみえる。その言い回しには教養の一種の特権化のにおいもあって、現在ではそれはある程度、平準化されたから、という面もあるだろうが、それ以上に、大学の教育課程に占めていた教養部の解体を通じて教養の時代の終わりを促し後押しした結果、加速された現象かもしれない。
かわりに台頭したのが「効率」だろう。それは「教養がじゃまをして」というような対処を、目的合理性を欠いた行動とみなす立場の展開である。目的が定まれば、精神的・物理的、そして時間的にいかにローコストでそれを実現し、成果を手に入れるか、その最短性こそがなにより優先され、二者択一の選択を繰り返す場に、教養というかたちのその人のいわば人間が投企されることはないのだろう。そう考えなければ、わたしのような昔人間には理解不能な出来事が、わたしの職場から永田町に至る日本だけでなくアメリカをはじめ世界規模で頻発している。「戦時昭和」の人間模様はけっして過去のことではない。
コロナの時代でなかったなら、友人諸氏はきっとそれぞれに祝杯の誘いをかけてくれたことだろう。いつもなら飲もうと言う人たちも、まあ、高齢者同士だからお互い誘うのがはばかられるのだ。といって、オンライン飲み会のような新様式にはとてもなじめない。東京大空襲のあと、焼け出された永井荷風は、勝山(岡山)に疎開していた谷崎潤一郎を訪ねる。先輩に対する谷崎夫婦の接遇は、宿や酒食から切符の手配に至るまで実に行き届いているばかりか、許されるかぎりの贅をつくしたものだった。荷風は、なかなかお目にかかれなくなった白米や牛肉そして日本酒に、涙を流さんばかりに「欣喜」する。モノがない時代ゆえの欣喜落涙でもあるが、戦火をくぐり抜けてともにする知己との飲食なればこその感慨も大きかったにちがいない。いまは、幸いモノはある。しかし、人間関係の一次的な直接性がおびやかされている。知己を目の当たりに実感する荷風の欣喜落涙は、現在、我々にどのように可能だろうか。