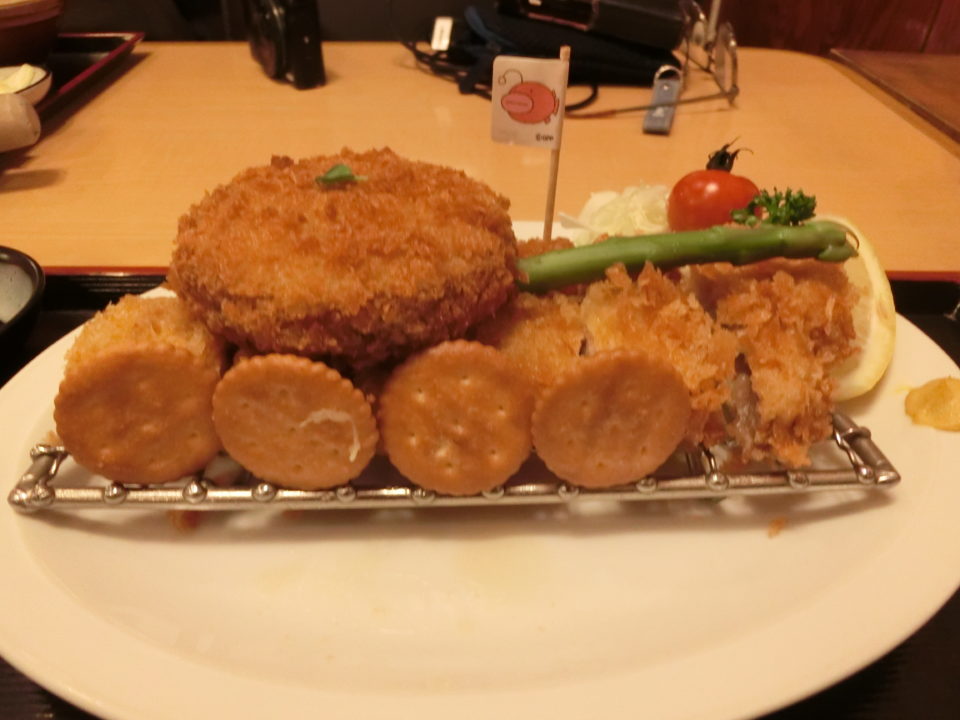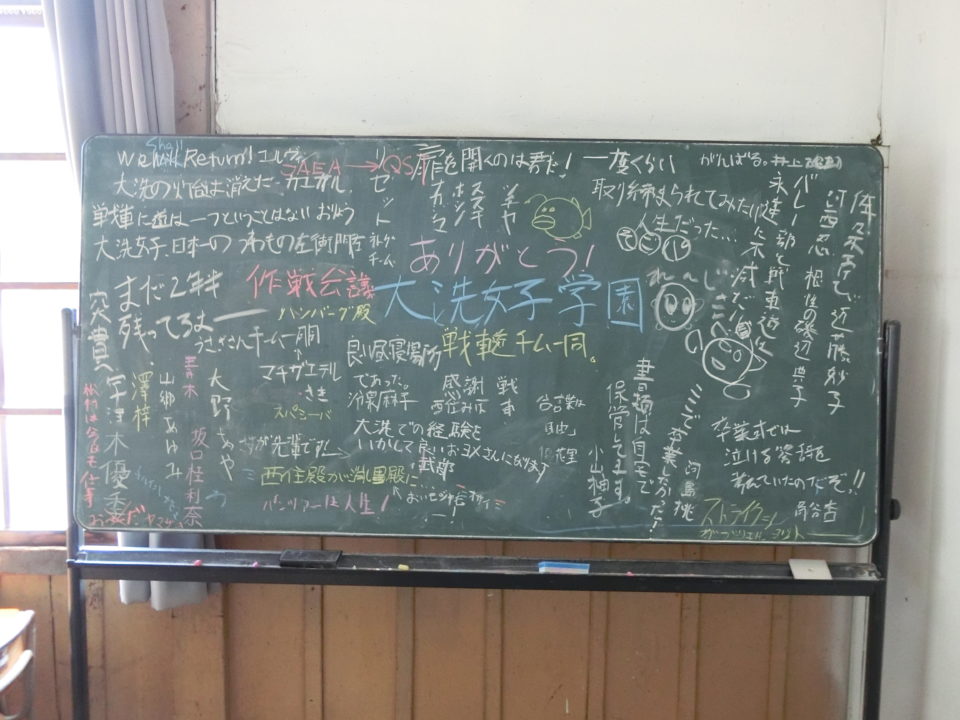難波祐子(なんば・さちこ)
(キュレーター。東京都現代美術館を経て、国内外での展覧会企画に関わる。著書に『現代美術キュレーター・ハンドブック』『現代美術キュレーターという仕事』〔ともに青弓社〕など)
「作品」は誰が作るのか
これまで美術館をはじめとする、「作品」を展示する環境と、その歴史的な成り立ち、また「作品」が展覧会での展示を通して「作品」として成立するうえでのキュレーターの役割などについて見てきた。これらのギモンでは、アーティストが「作品」を作り、キュレーターがそれを「展示」する、という大前提を基本にしていた。だが、ギモン1で少し触れた1990年代以降に急増した参加型の作品は、作品が成立するうえでアーティスト以外の複数の人が関わることが多く、こうした「大前提」にさまざまな問いを投げかけている。
ところで、「作品」を複数の人による協働作業で作る、という行為自体は、美術史的に見れば、実は新しいものではない。ヨーロッパでは、特に中世からルネサンス期にかけて工房制度が長きにわたってあり、絵画の制作は、アーティスト個人の表現活動というよりは、工房で分業による集団作業でおこなわれていた。近代以降、師弟関係に基づく工房制度の時代とは、美術作品の制作のあり方も様変わりしたが(1)、現代美術では、単一の作者としてのアーティストという存在にかわって、地域住民や観客が作品の制作に関わることがごく一般的になってきた。例えばギモン1に登場したリクリット・ティラヴァーニャの「無題(デモステーション)」シリーズを思い起こしてみよう。展覧会の会期中、会場に用意された仮設舞台を、地元のバンドや俳優といった人たちが活用していき、そのプログラム自体が、作品の完成に結び付く。ティラヴァーニャは、作品のための設えを用意し、ファシリテーター的にそこでの出来事を見守る。このような展覧会においては、「作品」は誰が作ると言えるだろうか。そしてこうして作られた「作品」は、誰のものと言えるだろうか。またキュレーターは、こうした作品の「展示」に対して、どのような役割を担うのだろうか。
今回のギモンでは、「作品」とは何かを考えるなかで、特に「作品」の作り手にまつわるギモンに着目し、近年盛んになっている参加型の作品や、アーティスト以外の人々との協働制作の形式をとるような作品を中心に、具体的な事例をいくつか見ながら、参加者・観客側の視点から考えていこう。またそれを受けて、あらためてキュレーターの役割についても考察してみたい。
「参加型」アートとは?
ここで「参加型」という言葉の、本稿での位置づけを明確にしておきたい。そもそも展覧会は、観客が来て、作品を鑑賞する、という行為のもとに成り立っている。絵画や彫刻作品を観て、それについて観客が何かを感じる、ということも広義の「参加」にはなるかもしれない。あるいは、新型コロナウイルスの感染拡大による美術館休館ですっかりおなじみになった、オンラインでのライブ配信型の作品やVR(仮想現実)で撮影された展覧会を視聴することも「参加」と言えるだろう。逆に作品との直接的な接触などを伴ういわゆるインタラクティブ(相互作用的)な作品を思い浮かべる人もいるかもしれない。ボタンを押したら何かが動作するとか、観客が展示室に入るとセンサーが観客の動きを感知して映像のプロジェクションや音などに反映される、といったタイプの作品だ。極端な話、どの作品も、最終的には鑑賞者がいてはじめて作品が完成する、とも言える。だが、本稿で主に扱う「参加型」の作品は、観客や地域住民などが参加するプロセスそのものが、作品成立に深く関わっている類いのもの、そしてその結果を「展覧会」という枠組みのなかで展示する作品を論じることにしたい。例えば、台湾出身でニューヨーク在住のリー・ミンウェイは、1990年代から作家自身と参加者による直接の対話に基づくプロジェクトや、展覧会場を訪れた人が、リーの設えた環境で、何らかの作業や行為をすることを作品化したプロジェクトを数多く発表している。ニューヨークのロンバード=フレイド・ギャラリーで2000年におこなわれた「プロジェクト・ともに眠る(The Sleeping Project)」では、画廊のなかに作られた隣り合ったベッドをもつ寝室空間で、抽選により招かれたゲストがリーと一夜をともにし、さまざまな出来事を語り合う。ゲストは、普段、自分が眠る際に手元に置いている時計や写真立てなどの私物を持参し、ベッド脇のナイトテーブルに置いて帰る。会場を訪れた人は、ナイトテーブルの上に残されたものを見ながら、そこで交わされた会話などを想像する。この作品は、もともとリーが高校生のときに夜行列車でパリからプラハに向かった際に乗り合わせた年配のポーランド人男性と一晩を過ごした体験から着想を得ている。その人物はホロコーストの生還者で、当時の収容所での様子や体験などをリーに語り終えたあと、眠りについた。だがリーは、話を聞いて、その昔、もしかしたらいま、自分が乗っている列車と同じ線路のうえを走っていた列車に夜通し乗せられて、朝まで生きながらえなかった人もいたかもしれないなどと思いをめぐらせ、眠ることができなかった。この私的で強烈な体験をもとに、何年もたってから、「眠る」ことと、「(誰かと)ともに眠る」ことについて、作品にしようと考えたのがこのプロジェクトだったと彼は語っている(2)。このように自分以外の誰かと行為をともにすることが、リーの作品の根幹をなしている。その行為は、作家と直接協働作業をおこなう場合もあれば、展覧会場で観客の手に委ねられることもある。例えば「プロジェクト・手紙をつづる(The Letter Writing Project)」(1998年)では、会場内に障子の部屋を思わせる、すりガラスと木枠で三方を囲まれた3つのブースが設けられ、観客は、そのブースのなかに入って手紙を書いたり、読んだりすることができる。ブースのなかには机と便箋と封筒が置いてあり、観客は、誰かへの感謝、許し、あるいは謝罪の手紙を書くように促される。手紙を書き終えたら、持ち帰らずにブースの内側の壁に設えられた木枠に手紙を挟んでその場をあとにする。手紙の封はしてもしなくてもいいが、封をしていない手紙はほかの人が自由に読んでいいことになっている。そして封筒の表に送り先の住所が書いてあれば、作家か美術館スタッフがかわりに投函してくれる、というプロジェクトだ。ここでは、手紙を書く、あるいは読むという観客の参加、そしてその行為によってそれぞれが個人のストーリーに思いをめぐらすことが作品の重要な一部になっている。
リーやティラヴァーニャのような参加型作品は、最終的な発表の場が美術館やギャラリーでの展覧会のことが多いが、こうした地域住民や観客の直接参加などを伴う作品は、1990年代後半から、リレーショナル・アート、コミュニティ・アート、あるいはソーシャリー・エンゲージド・アート(社会的な参加を伴うアート)といった名称で、地方自治体や学校でのアートプロジェクトやワークショップとして美術館やギャラリー以外の場所でも実施される機会も多く見られる。例えばイギリスのアーティストであるジェレミー・デラーは、何らかの共通項をもつ地域住民など特定のコミュニティと協働して作品を制作することで知られている。初期代表作の一つ、『アシッド・ブラス』(1997年)は、街中のブラスバンドと、電子音楽とクラブ・カルチャーに端を発するアシッド・ハウスという一見全く異なる音楽文化の間に奇妙な共通性を見つけたデラーが、イングランド北部の町ストックポートを拠点として活動するブラスバンドにアシッド・ハウスの生演奏を依頼したことから始まったプロジェクトだ(3)。『アシッド・ブラス』は瞬く間に人気を博し、イギリス各地で演奏されたほか、アルバムも発売されて、バンドのレパートリーとしても演奏される長期プロジェクトになった。この作品についてデラーは、自身の制作のターニング・ポイントだったと述べている。「モノ(オブジェ)を作らなくてもいいんだ、と気づいた。こんなふうにイベントをやって、何かを巻き起こして、それを人々と一緒にやって楽しめばいいんだ。乱雑で野放しでオープンエンドなプロジェクトをすることで、伝統的なアーティスト像にこだわらなくてもよくなった。ブラスバンドが僕を解放してくれたんだ(4)」。デラーのプロジェクトは、単なる音楽のコラボレーションの域を超えて、それぞれの背景にある社会史を浮き彫りにし、異なるコミュニティ同士の新しい出会いを生み出すなど、さまざまな広がりを見せるプロジェクトになった。このように参加型作品の多くは、絵画や彫刻などのように物質的な「作品」として残るのではなく、何らかの出来事が起こり、そのプロセスや結果が共有されることそのものが「作品」になることを特徴としている。よって作品の形態も美術館での展示だけではなく、街中などでおこなわれるパフォーマンスやイベント、あるいはコンサートや映画など多岐にわたるケースも多い。だが、こうした作品を実現するにあたっては、展覧会やアートプロジェクトなど、アートの枠組みがその背景にあることがほとんどである。
デラーは、このような手法を国際展の場でも取り入れている。例えば、ギモン1で少し触れたミュンスター彫刻プロジェクトは、ドイツの中世の面影が色濃く残る街ミュンスターで10年に一度開催される大型の国際展だが、デラーは2007年に参加した際に次回開催の10年後である17年まで続く作品を発表した。デラーは、ドイツで盛んな「クラインガルテン」、あるいはクラインガルテン運動を広めたシュレーバー博士の名にちなんで「シュレーバーガルテン」と呼ばれる市民農園に着目した。そしてミュンスター郊外にある50以上のクラインガルテン協会に、各農園での四季折々の天候や植物の移り変わりの様子、各協会での社会的・政治的な活動などを10年間にわたって日誌に記録してもらうよう依頼した。10年後の17年には、そのうちの一つのクラインガルテン内にある小屋に、各農園の10年にわたる日誌約30冊を自由に閲覧できるスペースを設けた(5)。各日誌にはそれぞれの農園の個性が反映されていて、家族やメンバーで集まってバーベキューやパーティーをしたときの写真や、収穫された野菜の写真、新聞や雑誌の切り抜きなどが思い思いにスクラップされ、子どもたちが描いた絵やメンバーが書いた詩などとともにつづられていった。またミュンスター彫刻プロジェクトに訪れた人も、メッセージやイラストなどを記すことができるように、農園のメンバーが使っていたものと同じ様式の白紙の日誌も用意され、会期中次々と来場者によって書きつづられていった。
クラインガルテンの活動自体は、デラーの呼びかけとは関係なくドイツで200年以上の長きにわたって市民に親しまれている営みである。そのため、それだけでは「作品」にはならない。だが、アーティストが展覧会という仕組みや仕掛けを使って、普段であれば、関わっている当事者たちも気がつかないような人々の市民農園での活動を、当事者たち、市民農園のことを知らない人々、国内外から集まる展覧会の観客に、目に見える形で提示、共有する場を農園のメンバーたちと10年という長いスパンをかけて作っていくことで、一つの「作品」になった。このように参加型アート作品は、それを通してさまざまな人々が有形無形のつながりをもつことが特徴である。また、参加型作品の大半は、長くても2、3ヶ月程度の会期の展覧会に向けて準備され、そのあとは終了してしまうのだが、『アシッド・ブラス』やクラインガルテンでのデラーの息の長い活動は、展覧会やアート作品の枠組みを横断しながら、それらを超えて、参加者側がその試みに自発的に参加し、ともに作り上げていると言えるだろう。また通常は、展覧会での発表が作品の最終的な完成形だと見なされがちな参加型作品だが、このように長期のプロジェクトでは、どこまで(いつまで)参加すれば、その作品が完成したと言えるのか、どこからどこまでが「作品」なのか、という問いを図らずも投げかけている。
「作品」は誰のものなのか
さて、ここでいま一度考えたいのは、こうした協働制作などを伴う参加型作品は誰のものなのか、またどこまでが作家の手によるもので、どこからが参加者の手によるものなのか、というギモンである。それを考えるうえで、2000年にロンドン北部の小学校の児童がイギリス人アーティストのトレイシー・エミンと作った作品をめぐるエピソードを1つ紹介したい。この作品は、ロンドン北部と東部にある教会や礼拝堂などの宗教施設でおこなわれた「聖なるところにあるアート(Art in Sacred Spaces)」という著名な現代美術作家12人によるグループ展の一環として展示されたものだった。エミンは、小学校の8歳児12人に「美しいと思うものを教えて」というテーマで、言葉を募るワークショップをおこなった。そして「木」「日の出」「イルカ」「おばあちゃん」などの単語をつづったフェルトの文字が、子どもたちが持ち寄ったカラフルな端切れに子どもたち自身の手によって縫い付けられていった。最終的には、こうして制作したパッチワークでできたキルトを、地元の教会の祭壇に1週間展示した。ここまでは、よくある地元の子どもたちとのワークショップで協働制作された作品の話で、普段は自らのプライベートを暴くようなスキャンダラスな作品で知られるエミンの別の一面を見せるプロジェクトで終わるはずだった。だが、話はこれで終わらなかった。展覧会から約4年たった04年に、この作品をめぐる騒動が起きたのだ。作品を保管していた小学校が、この作品を長期間、安全かつ劣化しない形で保管するための方策として、アクリル製の展示ケースを製作してはどうかと見積もったところ、4,000ポンドかかるとわかった。そのような費用を捻出することが難しいと判断した学校が、苦肉の策として、同作品を競売にかけて、その売り上げ(3万ポンドから3万5,000ポンド相当の見込み)を同校の芸術棟を充実させるために有効活用しようとした。だが、オークションハウスで有名なサザビーズは、この作品をまずはエミン本人が自身の作品だと認めないかぎり、作品の価値は端切れ代程度にしかならない、と学校側に伝えた。これに対してエミンは、もし作品を競売にかけるのであれば、それを自分の作品だと認めることを拒否するばかりか、作品の返還も求めると言い出す騒ぎになった。最終的にはこの騒ぎの顛末は、展示ケースのための費用4,000ポンドをエミンが負担する、ということで決着がついた(6)。作品を実際に00年に制作したときには、エミンがコンセプトを考え、子どもたちとのワークショップにも立ち会い、エミンが参加するグループ展の一環として展示された。だが、このキルト作品が「トレイシー・エミンの作品」として、いざ評価額をつけるとなったとき、それは純粋に作家の作品と言えるのか、それとも協働制作者である子どもたちもまた作家と言えるのか、また作った作品は一体誰のものなのか、という作家と作品の曖昧な関係性を図らずも明るみに出すことになった。一口に「協働制作」と言っても、参加している側の作品への作り手としての意識や作品に対する思い入れ、そして作家自身の参加者や作品に対する考え方は、作家によって一律ではないし、同じ作家による同じ枠組みで実施されたプロジェクトであっても、関わる人々が変われば異なってくるかもしれない。ここで「作品」の作り手についての考察をもう一歩進めていくうえで、エミンのプロジェクトとは全く異なる参加型アートを実践している、藤浩志の「かえっこ/Kaekko」を紹介したい。
システムとしての「作品」
「かえっこ」は、藤浩志が2000年から始めたプロジェクトの総称で、家庭で不要になったおもちゃを交換するという仕組みそのものを作品化した、いわばシステム型の作品である。もともとは1997年頃に藤の家で生じたゴミ出し問題に端を発し、家庭内でゴミを排出せずに、ゴミを再利用して表現行為に転換する「家庭内ゴミゼロエミッション」プロジェクトが「かえっこ」へと繋がった。そこから2000年の福岡アジア美術館での開館1周年イベントの一環として開催されたアーティストフリーマーケットに、藤が自身の子どもたちと出店したことがきっかけになり、その後、子ども向けのワークショップとして国内外の美術館やアートプロジェクトの場で「かえっこバザール」などの名称で盛んに開催されるようになった。そのなかで、交換したおもちゃがかえっこバンクで「カエルポイント」として発行され、その貯まったポイントで気に入ったおもちゃを購入したり、オークションをおこなったりする仕組みが生まれた。また、おもちゃをもってこなくても、スタッフとして「かえっこ」の運営を手伝ったり、ワークショップの活動に参加するとカエルポイントがもらえるなど、おもちゃの交換をめぐってさまざまな活動が誘発される仕組みが整えられていった(7)。のちにこのシステムそのものを「Kaekko」というローマ字で藤は使い分けている。ここで注目したいのは、この「かえっこ/Kaekko」が、瞬く間に美術館やアートプロジェクトでおこなわれるアーティスト藤浩志のワークショップ型プロジェクトから、誰でも開催できるシステム型プロジェクトとして広まり、環境問題に関心があるNPOや子育て支援グループ、街づくりの関係者など、従来のアートに従事する層とは異なる団体などがこぞって開催するようになったことだ。「かえっこ」を開催するにあたっては、藤の妻である藤容子が担当するかえっこ事務局に連絡をすると、開催情報のウェブ掲載などの広報協力を受けることができるほか、カエルポイントを押すためのカエルスタンプやかえっこカードなどの開催に必要なツール、最初のおもちゃの貸し出しなどを受けることができる。だが、ここで「かえっこ」がほかの参加型作品と大きく異なる特徴的な点は、「かえっこ」の開催の規模や目的は、主催者の裁量に任されているということだ。つまり「Kaekko」は、システムとして誰でも使えるようになっていて、そこにはもはやアーティスト藤浩志の名前は登場しない。私も当初は「かえっこ」を藤のワークショップ型プロジェクトとして認識して、実際に美術館やアートプロジェクトの現場で開催された「かえっこ」を見てきたのだが、ある日、ローカルのニュース番組で「かえっこ」が取り上げられていたのを目にして、ちょっとしたショックを受けた。その番組では、とあるNPO団体(子育て支援系だったか、街づくり系だったかは記憶が定かではないが)の女性の主宰者が、「かえっこ」を開催していて、その活動について生き生きとした口調で語っている様子が取材されていた。そこに映る映像は、以前、藤のプロジェクトとして見ていた「かえっこ」そのものだった。おもちゃを交換する仕組みや、カエルポイント、運営をお手伝いする子どもたちなどが、レポーターにより「市民による素敵な取り組み」風に紹介されていた。だが、ニュースレポートはそこで完結し、それがもともとは藤浩志の発案だったことや、アート作品であることなどには全く言及がなく、当時、「え、これって藤さんの作品だよね? 著作権、大丈夫なの?!」とあらぬ心配をしてしまったことを覚えている。藤は「かえっこ」について次のように述べている。「《かえっこ》は最初から「仕組み」の表現作品だと考えていました。使う人がコンセプトやプログラムを決めることでどんどん変わっていくタイプの作品です(8)」。さらに藤は、このシステムとしての「Kaekko」をそこで終わりにせず、それを利用して『Happy Paradies(ハッピーパラダイズ)』というインスタレーション作品として再び一つの形ある「作品」として引き戻す作業をおこなっている(9)。『Happy Paradies』は、マクドナルドの子ども向けのおもちゃ付きセットで知られる「ハッピーセット」でもらえるおもちゃと、それに類似したおもちゃ約14,000個、おもちゃの一部や破片約250個、おもちゃで作られた『夢の鳥』や『Toys Saurus』などの複数のオブジェからなるインスタレーション作品である。これらの素材になった大量のおもちゃは、全国で開催される「かえっこ」事業の終了後に残ったおもちゃが返却される過程で、次の「かえっこ」へと循環して活用されることがない、いわば「子どもたちでさえ不要と思うおもちゃ」である。それらを色や形、大きさ、キャラクターなどによって数百種類に分類し、インスタレーション作品の素材として用いている(10)。さらにこの作品を展示する際には、「美術大学の学生との関係を尊重し、同じような、あるいは理想的にはもっと若い、まだ感性が柔らかい状態の学生」が、作家の指示どおりではなく、「自らの感性と意志で自由に並べること」を重視している(11)。このように「Kaekko」から派生した『Happy Paradies』もまた、形ある「作品」でありながらも、複数の他者の手による開かれた展示のシステムを提供している作品になっている。エミンの作品で争点になった協働制作による作品の「作家性」は、藤の「Kaekko」や『Happy Paradies』では軽やかに解体されてしまい、物理的なモノではなく、システムそのものに宿る。藤のこのような実践は、小説などの文学作品の作者と読者の関係を想起させる。小説などの作品を書くのは作者だが、その作品をめぐる多様な解釈は、実際に作品を読む読者一人ひとりの手に委ねられていて、作者自身の作品に込めた意図に必ずしも縛られることはない。ここで参加型アートにおける作家についての考えを深めるための手がかりとして、文学作品での作者と読者の関係をめぐる議論を少しのぞいてみよう。
参加型アートの「作者」とは?
文学作品などの「作者」については、1960年代のフランスで、ロラン・バルトが『作者の死』(1968年)、ミシェル・フーコーが『作者とは何か?』(1969年)と相次いで論考を発表している。なかでもバルトは、「作者の死」という象徴的な言葉で、テキストをめぐる作者と読者の関係について論じていて、その考え方はアートの理論にも大きな影響を与えている。バルトは、「一遍のテクストは、いくつもの文化からやって来る多元的なエクリチュール〔引用注:「書かれた言葉」〕によって構成され(12)」た「引用の織物である(13)」と言う。そしてこの多元的なエクリチュールによって織物のように編まれた作品の「多元性が収斂する場」は、「作者ではなく、読者である」とし、次のように結論づける。「読者の誕生は、『作者』の死によってあがなわれなければならないのだ(14)」。つまり、作者が書いた織物のようなものである作品は、作者の手を離れて、読者によって自由に解釈されていくというのだ。それまで作者というのは、作品の意図や解釈を支配する神のような存在と思われていた。だがバルトの「作者の死」は、作者ではなく、作品の受け手である読者がその作品を読む行為によってそれぞれの意味を見いだすと説く。これは、従来の作者と作品の関係性を根本から問い直すような考え方だ。それは、まるで美術作品の唯一の作り手とされてきたアーティストと作品の関係性が、参加型アートの台頭によって揺らぐさまと呼応しているかのようだ。例えば、先に見た藤の「Kaekko」システムは、参加者・鑑賞者によって藤浩志という一人のアーティストの手から離れて、自由に運用され、享受されている。だが、このことは、「Kaekko」というシステム型作品を生み出した藤自身の存在を完全に消し去ってしまうわけではない。
バルトが言う「作者の死」に対して、フーコーは作者について、実在するものとして異を唱えている。ただし、ある一冊の書物を記した一個人としての作者、という存在としてではなく、作者というものが果たす「機能」に着目し、作家と作品の関係性をさまざまな角度から分析している。例えば、ジークムント・フロイトというのは単に『夢判断』という本の作者であるだけではなく精神分析学の創始者であり、それによって精神分析に関するさまざまなテキスト、概念、仮説などの言説を生み出す機能をもっている(15)、と説く。フーコーは、「機能としての作者」は、「言説の世界を取りかこみ、限定し、分節する法的制度的システムと結びつく」と言う。そしてそれは、時代や文明の形態によって「一律に同じ仕方で作用するものではない」と指摘している。さらにフーコーは、こうして生まれた言説は、それを生み出した「ある現実の個人」に帰属させるのではなく、「複数の立場=主体を同時に成立させることができる(17)」と述べている。美術作品に当てはめて考えてみると、バルトやフーコーの「作者」と「作品」をめぐる論考は、参加型アートにおいて、非常に興味深い視点を与えてくれる。作家と鑑賞者が、それぞれ作品の「作り手」と「受け手」としてはっきりと分断されていた従来の作品と異なり、参加型アートの場合、鑑賞者も書き手になり、織物のように作品を作り出していく。ただしそこで作者はバルトが言うような「死」を迎えるのではなく、フーコーが言うように作者も鑑賞者も複数の作り手になり、多元的・主体的に作品を形成していく。それぞれの作家の作品は、もともとは作家の個人的な原体験などから着想を得て、生まれているが(リクリットの祖母の家での料理、リーの夜行列車での体験など)、それが参加者を招くことで、それぞれの参加者個人の体験や経験などと重なり合いながら、「作品」になっていく。そういった意味では、「作品」は作家一人のものではないが、作家自身の存在を否定するものでもないと言えよう。そしてフーコーが言うようにこうして生まれた「作家」や「作品」をめぐる言説は、それを取り巻く社会的なシステムと結び付いていて、その背景になる時代や文化によって、多様な姿を見せている。
参加型アートでのキュレーターの役割
これまで協働制作を伴う参加型の作品における、作家と参加者・鑑賞者の関係について見てきたが、ここで少し視点を変えて、こうした作品でのキュレーターの役割についても考えてみよう。先に紹介したデラーのような実践は、ソーシャリー・エンゲージド・アート(社会的な参加を伴うアート)という枠組みで論じられることも多い。ソーシャリー・エンゲージド・アートというカタカナの用語は、特に2000年代になって日本でも使われる機会が増えてきた。これらの多くは、美術館のなかではなく地域のコミュニティなどで実践され、ときにその地域が抱える社会的な問題を解決するための手立て、あるいはそうした問題をあぶり出すためのツールとして、アートの手法を使っていることが多い。イギリスの美術史家クレア・ビショップは、こうしたソーシャリー・エンゲージド・アートの実践を著書『人工地獄』で、美術史や美術批評に照らし合わせながら、パフォーマンス、演劇、美術教育なども含めた幅広い参加型の実践を、多数のアーティストや参加者たちへのインタビューなどを交えながら多角的な視点から紹介し、分析を試みた。そこで彼女はキュレーターの役割について、次のような重要な指摘をしている。「各プロジェクトに責任を持ち、ときに――しばしばアーティスト以上に――一部始終に立ち会う唯一の存在となるキュレーターの手に、参加型アートの主な語り手としての権利が委ねられる」。ビショップは、そうした「キュレーターたちの語りにおいて、批評的な客観性が排されていること」に失望し、そのことが彼女の研究の重要なモチベーションになったと述べている。ビショップが言うとおり、プロジェクト全体を把握しているキュレーターや、それについてキュレーターの言葉を頼りに研究・批評する者にとって、特に「プロジェクトの中心要素に人間関係の形成があり、それが特定の主体によるリサーチに否応なく影響を与えてくるような場合」に「かかわりが深まるほど、客観的で居づらくなる(18)」ことは確かだ。こうした状況に対して、ビショップは美術史家としての立場からあくまでも客観的に分析を試みるが、そもそも、参加型プロジェクトで、当事者としてのキュレーターが参加者、アーティストとともに人間関係を形成していくのは、ある意味必然的な結果であり、逆にそうした人間関係が形成されなければ、しばしば長期にわたるプロジェクトを遂行することは不可能になるだろう。そのプロセスのなかで、キュレーターは、そのプロジェクトの推進者、アーティストや参加者の伴走者であることが求められる。同時に、最終的にはその結果を展覧会やアートプロジェクト、あるいはカタログや報告書として外に向けて発信していく役割も担う。そこでビショップが言うような客観性をどこまで担保する必要があるかは、プロジェクトの目的や、対象にする観客によっても異なってくるだろう。ここで最後に参加型アートにおいて、こうした作品は誰のために作るのかについてあらためて考えてみたい。
「作品」は誰のために作るのか
協働制作を伴う参加型アートで誰がその作品を享受するのか、ということを考えると、一義的には、そのプロジェクトに直接参加したある特定の個人やグループ、コミュニティの人たち、ということになるだろう。だが、それがアートの文脈で語られるとき、作品はその一義的な参加者のためだけのものにとどまらない。作品の展示やパフォーマンスのお披露目、映像上映などで、それらを鑑賞するより多くの人々が、一義的な参加者たちの体験を追体験したり、各々の記憶や体験、人生のストーリーなどと結び付けたり、重ね合わせたりしていく。もちろん、プロジェクトの協働制作を直接担った参加者と、それを展示室などで鑑賞する鑑賞者が全く同じ体験ができるわけではないだろう。それでも、一つの「作品」として展覧会の文脈で発表され、多くの人に共有され、享受されることで、最終的には、広義の「参加型作品」が成立すると言える。また参加型作品の作り手は、作家一人にとどまらず、参加者、鑑賞者も主体的にそのプロセスに関わり、キュレーターも加わって、多元的な織物のような「作品」とそれを取り巻く言説を作り上げていく。
あらためて、「作品」とは何か、というギモンに立ち返ると、「作品」を成立させる諸条件は、作品を取り巻く環境、歴史的背景、作品制作の方法論など非常にさまざまな要素が絡み合っていることがわかる。参加型の「作品」をめぐって、作品が一人の作家により作り出され、完成し、展示されるもの、という前提から大きくはみ出していくなかで、作家と観客の間にある境界線が曖昧になっていき、アーティストとキュレーターの役割も交錯していく。従来の作品を作る人=作家、見る人=観客、作品を選んでその場を設える人=キュレーターといった構図がより有機的・複合的に絡まっていることを、これまで見てきた事例からも垣間見ることができる。本ギモンの後半では、参加型作品をめぐる作家と観客、キュレーターの関係について少し駆け足で論じたので、消化不良を起こした方もいるかもしれない。それらについては、これから続くギモンでまた別の視点を交えながら、あらためて解きほぐしていきたい。
注
(1)ただし、こうした工房制度スタイルは、現代美術でいまでも一部健在であり、それについては近い将来、また別の機会に論じてみたい。
(2)“LEE MINGWEI: THE SLEEPING PROJECT, 2000”(https://www.perrotin.com/artists/lee_mingwei/550/the-sleeping-project/48708)。オリジナルの作品では、交わされた会話は録音され、会場で聞くことができたようだが、近年の再制作では、ゲストが持ち込んだオブジェがナイトテーブルに置かれるだけになっている。なお、本稿に登場するリーの作品の日本語タイトルは、すべて森美術館「リー・ミンウェイとその関係」展(2014年)に掲載されているものを採用した。
(3)『アシッド・ブラス』については、BBC2で2012年2月24日に「The Culture Show」で放映された「Acid Brass: Jeremy Deller」に簡潔にまとめられている。“Acid Brass – Jeremy Deller – The Culture Show (24/02/2012),” YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=gBJxMQGYXM4)
(4)“Acid Brass, 1997,” Jeremy Deller(https://www.jeremydeller.org/AcidBrass/AcidBrassMusic.php)
(5)Skulptur Projekte Münster 2017カタログ、170ページ
(6)この事件については複数のイギリスメディアが報道しているが、本稿は以下のウェブサイトを参照した。“Blanket refusal,” The Guradian, March. 30, 2004(https://www.theguardian.com/artanddesign/2004/mar/30/art.schools),“Emin wants school quilt returned,” BBC News, March. 30, 2004(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/3584273.stm),“Emin pays to show school’s quilt,” BBC News, April. 6, 2004(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/3603787.stm)
(7)「かえっこ」誕生の詳しい経緯については、「《かえっこ》から《kaekko》までトークバトル」(『「かえっこについてかたる。」――かえっこフォーラム2008記録集』所収、水戸芸術館現代美術センター、2009年)16―29ページを参照のこと。
(8)同書24ページ
(9)『Happy Paradies』についての考察は、同作品を収蔵した金沢21世紀美術館の野中祐美子による以下の論考を参照されたい。野中祐美子「藤浩志《Happy Paradies(ハッピーパラダイズ)》――拡張する作品概念」、「Я[アール]――金沢21世紀美術館研究紀要」第7号、金沢21世紀美術館、2017年、92―96ページ
(10)同論文92ページ
(11)同論文95ページ
(12)ロラン・バルト「作者の死」『物語の構造分析』花輪光訳、みすず書房、1979年、88ページ
(13)同書85―86ページ
(14)同書88―89ページ
(15)ミシェル・フーコー「作者とは何か?」『作者とは何か?』清水徹/豊崎光一訳(ミシェル・フーコー文学論集1)、哲学書房、1990年、53―55ページ
(16)同書50ページ
(17)同書50ページ
(18)クレア・ビショップ『人工地獄――現代アートと観客の政治学』大森俊克訳、フィルムアート社、2016年、20ページ
Copyright Sachiko Namba
本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。
商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。