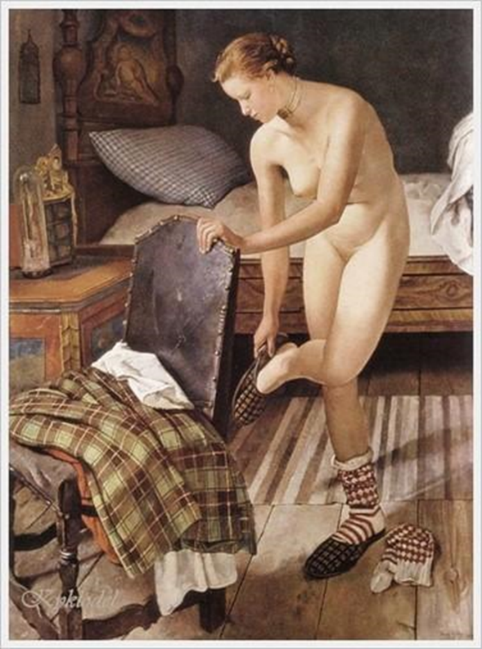伊東ゆう
「万引きする人って、そんなにたくさんいるんですか?」
初めて会う人が私のキャリアを知ると、必ずといっていいほどに驚かれる。そのほとんどが犯罪とは無縁の人たちだから、至極当然のことだろう。その一方で、過去の悪事を告白してくる人も珍しくない。
「学生のころ、捕まったことあるよ。ほしいけど高くて買えないもの、平気で盗(と)っていた」
万引きは軽く思われがちだからなのだろうか、あの店やこの店であんなものやこんなものまで盗っていたのだと、泥棒自慢をされることもある。
「このくらい、いいじゃないか」
「みんな、やっていることだ」
「捕まらないようにうまくやればいい」
これこそが万引き行為に至る被疑者の心理といえる。しかしながら悪い心を完璧に隠すのは難しく、その多くは挙動に表れ、いずれ私たちの目に留まることになる。万引きの成功体験をどんなに多くもっていても、絶対に捕まらないという保証はどこにもないのだ。
「万引きという言葉が軽いから、いっこうに減らないのではないか。万引きと呼ばずに窃盗と呼べばいい」――そんな意見をよく耳にする。万引きとは商業施設内での窃盗の形態や手口を表す言葉で、スリや空き巣、置引、ひったくりなどと同じように使われている。被害届や逮捕手続書などの罪名欄を見れば一目瞭然、「窃盗(万引き)」と記載されるのだ。「万引きは窃盗だ」と声高に叫ぶ人もいるが、そんな当たり前のことを周知する必要性は感じたこともない。万引きが悪いことだと知らない人は、まずいない。それに万引きを窃盗と呼ぶことになれば、調書などの罪名欄が「窃盗(窃盗)」になってしまう。現場知識がないための意見だろうが、耳にするたびに「そうじゃないんだよ」と説明したくなってくる。
同様の例を挙げると、オレオレ詐欺を特殊詐欺、盗撮行為を迷惑防止条例違反と呼んでいるが、被害が減るなどの変化は見られない。たとえ万引きを店内窃盗などに言い換えても、目に見える防犯効果は期待できないだろう。
ちなみに、私自身は捕まえた被疑者との会話で万引きという言葉を極力使わないようにしている。そのかわりに「泥棒」だとか「盗みにきた」という厳しめの言葉を多用する。再犯防止のために、少しでもいやな記憶を残してやりたいのだ。その日を最後にしてくれるなら、多少恨まれてもいい。これからも、そんな気持ちで被疑者と接していくつもりでいる。
最先端の防犯機器を用いた万引き防止対策は、ここ数十年でかなり進化している。防犯機器を導入する予算がある商店に限られるが、特に顔認証技術は向上していて、常習者情報の共有範囲を拡張する動きも盛んになってきた。防犯カメラ映像の解像度は急速に向上していて、人物の特定はもちろん、手にしている商品や紙幣、小銭までも明瞭に記録できる。映像検証による被害の特定が容易になった結果、被害届が受理される確率は高まり、その後の捜査で逮捕に至るケースも増えた。しかしながら、その多くは大量または高額の被害で、毎日一つだけ盗んでいくような高齢常習者までは対応できていない。私が推奨する「店内声かけ」は、こうした高齢常習者に対して効果的な万引き抑止対策の一つなのだが、新型コロナウイルスの影響で店内で他人と対話する機会は失われ、声をかけることさえもが難しい状況だ。犯行を思いとどまらせるすべは目合わせくらいで、それに気づかないままに実行されてしまえば、たとえ後期高齢者でも被疑者ならば捕捉するしかないのである。
防犯システムがめざすところは、無人店舗での防犯のAI(人工知能)化のようだ。多様化する精算方式に合わせて、各種セルフレジのほか、精算端末付きのカートを導入している商店も現れ、店舗の無人化を見据えた動きは加速している。支払いに利用する電子マネーなどには身分確認を経た個人情報が保管されていて、そうした状況下で犯行に及ぶとすればホームレスなどによる緊急避難的な行為しか思い浮かばない。そのような人の多くは電子マネーを利用できる環境になく、店舗への入場さえ許されないこともあり、人権問題にまで発展する可能性もある。万引きさせない店づくりの完成形といえるかもしれないが、人間味がなくなると商店としての魅力が欠けることは確かで、そのあたりの調整が難しそうだ。いずれにせよ、近い将来には店内でのすべての行動が記録されるようになることは間違いなく、私たちの仕事が形を変える日もすぐだろう。そうはいっても、万引きは社会情勢や時流に影響を受けやすい側面がある。犯行手口も進化することを忘れてはならない。
本書の多くは、2018年3月からウェブサイト「サイゾーウーマン」に隔週で連載してきた「オンナ万引きGメン日誌」をリライトして、現実の事件に近づけて再現したものだ。ここで初めて話すことだが、「オンナ万引きGメン日誌」の主人公である澄江のモデルは実在するが、その内容のほとんどは私自身の体験談なのである。女性向けサイトでの連載なので、読者が感情移入しやすいように考えてキャリア40年のベテランオンナGメン澄江を創作して書き始めたのだ。近頃は、澄江の話を聞きたいと各メディアから取材を申し込まれるまでになり、どこか心苦しく感じていた。そろそろ実情を告白しようかと思っていたところ、公私ともに深くお付き合いしている香川大学の大久保智生准教授から青弓社の矢野恵二さんを紹介してもらって、タイミングよく出版オファーを受けた。連載当初から「いつか書籍にしたい」と思いながら書いてきたが、こんなに早く実現するとは予想もしていなかった。自分を主人公にして書き直したいという気持ちもあったので、二つ返事で引き受けた次第だ。サイト内のアクセスランキングで1位になりそこそこ話題になった作品も複数所収しているので、ぜひお楽しみいただきたい。