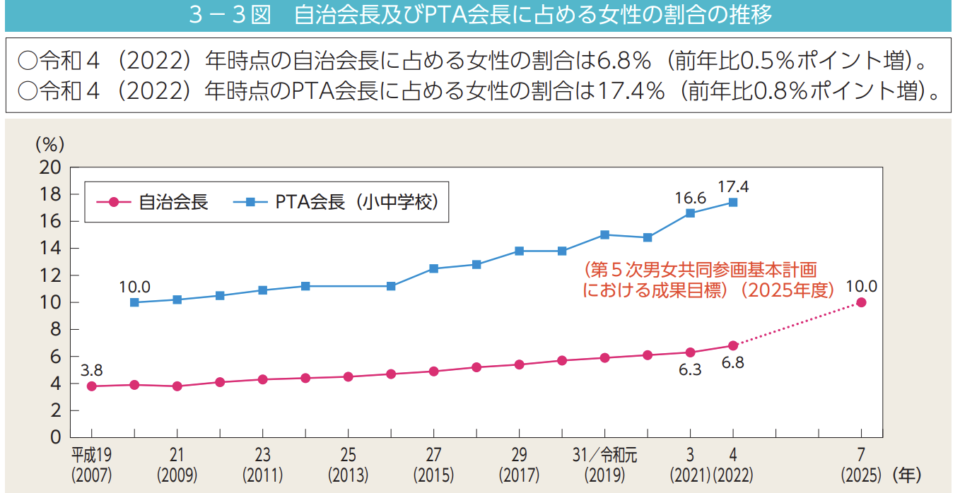平林直哉(音楽評論家。著書に『クラシックの深淵』〔青弓社〕など多数)
宮城道雄とも共演したフランスの逸材
1932年4月7日、フランスのヴァイオリニスト、ルネ・シュメーと、ピアニストのアンカ・セイドゥロヴァを乗せた浅間丸が横浜港に到着した。シュメーは国内で数々のリサイタルをおこない、日本の箏曲家・作曲家の宮城道雄と共演し、レコード録音までおこなった。そのため、シュメーは日本にとって忘れがたい演奏家の一人である。
シュメーは1888年、フランスのブローニュ=シュル=セーヌ(現ブローニュ=ビヤンクール)に生まれた。最初は声楽を学び、のちにヴァイオリンに転向、パリ音楽院でアンリ・ベルトリエに学んだ。のちにコロンヌ管弦楽団のソリストになり、ロンドンではヘンリー・ウッドが指揮するプロムナード・コンサートに出演、「ザ・チャーミング・アンド・スタイリッシュ・シュメー」と称される。ベルリンでは アルトゥール・ニキシュ、ウィーンではマーラーに認められ、ウィレム・メンゲルベルクとも共演している。1920年代から30年代がシュメーの全盛期だったようで、その後の活動については全く知られていない。なお、英語の「ウィキペディア」には1887年1月9日に生まれ、1977年1月2日に89歳で亡くなったと記されているが、真偽については不明。
1930年代までがシュメーの実質的な活動期間だったためか、彼女の録音は基本、小品しか残っていない。しかし、あらためてシュメーの録音をまとめて聴いたのだが、思った以上に底力があるヴァイオリニストだと痛感した。彼女単体のCDがこれまで発売されていないのは(LP復刻も同様だったと思う)、全く不当な扱いといえる。
以下は主にSPを聴いたもので、過去に何らかの形でCD化されたものはその旨を記してある。聴いたなかで最も古いものはガエターノ・プニャーニ(フリッツ・クライスラー編)の『序奏とアレグロ』(HMV 3-07920、1920年)である。ピアノはマルグリート・デルクール。序奏は間を大きめにとり、リズムはえぐるように力強い。ポルタメントも濃厚。アレグロに入ると、そのスピード感としゃれた崩し方が録音の古さを超えて伝わってくる。この曲の演奏でも、最も個性的な部類だろう。
同じくラッパ吹き込み(アコースティック)の逸品はエドゥアール・ラロの『スペイン交響曲』だ。これは第1、2、5楽章だけを片面(裏面は空白)に強引に収録したもので、カットはあるし、ピアノ伴奏ということで状況的には不利だが、演奏内容はかのジャック・ティボーにも匹敵する(HMV 3-07936、3-07937、3-07938、1921年)。最初このSPを入手したとき、てっきり「半端物(全曲そろっていないSP盤はこのように呼ばれる)」かと思っていたら、この3つの楽章しか録音されていないということだった(のちに別の曲と組み合わせて、SP盤2枚4面で再発売されている)。いずれにせよ、この遊び心と変わり身の早さは並みのものではなく、カットなしの全曲があればどんなによかっただろうと思わざるをえない。シュメーはティボーの演奏を聴いて影響を受けたかどうかは全くわからないが、両者を比較するとシュメーのほうがずっと男性的で力強い。なお、この片面盤のSPにはピアニスト名は記されていないが、HMVのカタログにはハロルド・クラクストンとある(再発売盤DB473、474にピアニスト名があるかどうかは未確認)。また、手元にあったプログラム(1932年5月28日、神戸)にもラロの『スペイン交響曲』が挙がっているが、このときは第1、4、5楽章が演奏されていた。
ここから先は電気録音。サン=サーンスの『序奏とロンド・カプリツィオーソ』(HMV DB887、1925年)もピアノ伴奏(クラクストン)ながら、両面にカッティングされていて、ラロのようなカットだらけのストレスはない。序奏は呼吸が深く、押し込むようなポルタメントがいかにもシュメーらしい。ロンドに入っても軽やかな身の運びと、濃淡を使い分けた甘さが実に見事。このSP盤は未入手で、「フランス・ヴァイオリンの粋を聴く」(CPCD-2006)(「クラシックプレス」第13巻付録、音楽出版社、2002年冬)を聴いた。
同じくSP盤は聴いたことはないが、『フランスのヴァイオリニスト』(グリーンドア GDCS0027)というオムニバス盤にシュメーが1曲だけ、ヴィエニャフスキの『華麗なるポロネーズ第2番』(1925年。録音年はCDではなくHMVのカタログによる)がある。これまた技巧の確かさと表現の多彩さがいかんなく発揮されていて、逸品だろう。ピアノはクラクストン。
チャイコフスキーの『夜想曲』、ハイドンの『メヌエット』がおさまったSP(HMV DB910、1925年)もシュメーらしさが十分にうかがえる2曲である。ピアノはハリー・コーフマン。
フランツ・ドルドラの『スーヴニール』(HMV DA811、1926年)は、シュメーの録音のなかでも屈指の出来栄えではないだろうか。開始早々、振り子のような絶妙なテンポ・ルバートに乗つた甘味音満載の旋律をちょこっと聴いただけで、体がとろけてきそうである。名曲だから録音も非常に多いが、シュメーの演奏は極私的3本指の一つだ。同じSPに含まれるポルディーニ(クライスラー編)の『踊る人形』(同じく1926年)もすばらしい。ピアノはともにデルクール。なお、『スーヴニール』は前述のCPCD-2006にも含まれる。
メンデルスゾーンの『春の歌』(無言歌より)も、いかにもシュメーらしい傑作である(日本ビクター VE1037、1926年)。この甘く切ない表情は『スーヴニール』と同等といっていい。ファリャの2曲を収めた『ムーア人の衣装』(7つのスペイン民謡)、『ホタ』(HMV DA814、1926年)も聴きもの。ことに前者のむせかえるような情緒は印象的だった。
エンリコ・トセッリとガブリエル・ピエルネの、それぞれ『セレナード』(日本ビクター VE1302、1927年)を収めたものもよかった。特にトセッリの柔らかく、ささやくような歌は一級品である。
モーツァルト(クライスラー編)の『ロンド』(日本ビクター VE7253、1929年)も傑出した演奏として記憶されるべきものである。主部は非常に勢いがあってスリリングであり、中間部は一転して上品な甘美さにあふれ、この対比が全く見事。この『ロンド』は『ヴァイオリンの名演奏家達――女性編』(ARC T20P503)で聴くことも可能(ただし、廃盤で入手が難しいかも)。
ヴィクター・ハーバート(ともにシュメー編)の『揶揄』『スウィート・ハーツ』抜粋(日本ビクター VE1498、1930年)は、曲としてはそれほど有名ではないが、録音がかなり明瞭であり、シュメーの個性が非常によく聴き取れる。『揶揄』はかつてシュメーと来日したセイドゥロヴァの伴奏。『スウィート・ハーツ』はオルガンや鐘が入り、ちょっと面白い響きがする。
録音データは判明できなかったが、『懐かしいヴァージニア』(日本ビクター VE1552)も音質がよく、シュメーを楽しむのには好適である。ピアノはセイドゥロヴァ。
シュメーが宮城道雄と録音した『春の海』(日本ビクター NK3002、1932年、LP復刻、CD復刻多数)は、聴きえたなかでは最も後年の録音ということになる。演奏は、和と洋がまことに美しく調和、融合されていて、シュメーの録音のなかでも独特の魅力をもっている。
この録音セッションが組まれたのは、おおむね以下のような経緯だった。シュメーが琴に興味があることを知った評論家の須永克己は、このことを宮城道雄に話をし、後日、須永はシュメーを連れて宮城の自宅を訪問した。シュメーは宮城が演奏する琴に非常に感銘を受け、特に『春の海』を気に入り、彼女は宮城にヴァイオリンと琴のための編曲を申し出た。宮城はこれを快諾、楽譜をシュメーに手渡すと、彼女は一晩で編曲版を完成させたという。後日、再度シュメーは宮城宅を訪れ、この編曲を2人で試奏、たった一度でぴたりと合ったという。この『春の海』のシュメー版の初演はシュメーの告別演奏会だった5月31日に日比谷公会堂でおこなわれ、アンコールされたという。
シュメーと宮城の共演盤は7月に10インチのSPで発売されたが、日本ビクターは値段を安く設定した効果もあって、当時としては破格の1万数千枚売れたという。のちにフランスやイギリスでも発売されたこの演奏だが、不思議なことに収録に関する情報(日付や場所)が全く得られない。唯一判明したのは、3通りのテイクを作って試聴し、そのなかで最も出来がいいとされたものが発売されたということ。複数の資料によると、別テイクが発売されたと記したものもあるが、これについても、よくわからない。私見では、一種類だけが市販されたような気がするが。
Copyright Naoya Hirabayashi
本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。
商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。