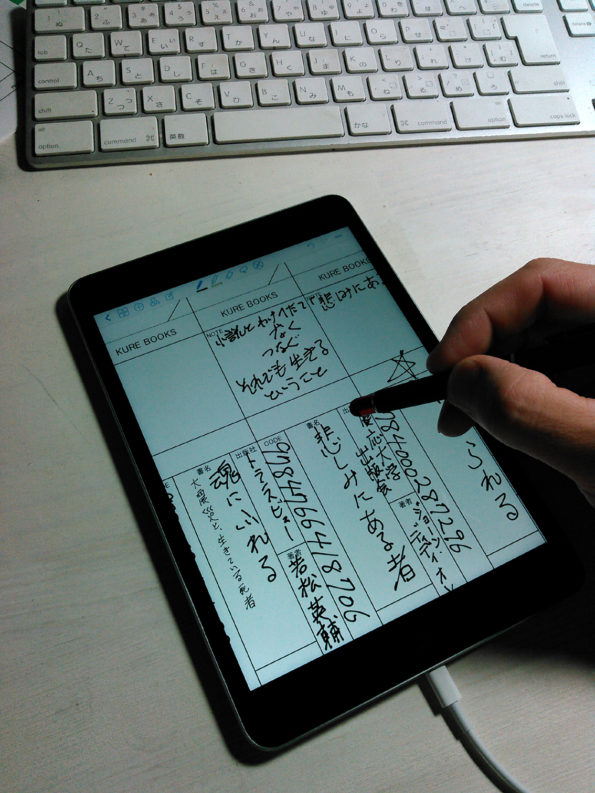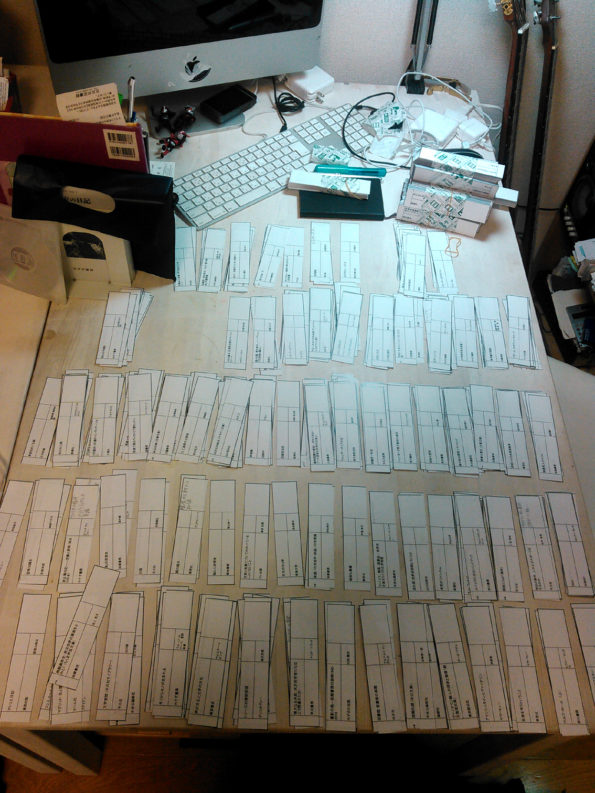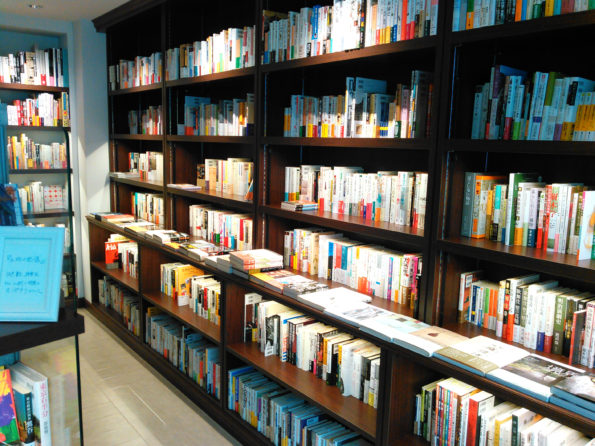太田省一
(社会学者。著書に『紅白歌合戦と日本人』〔筑摩書房〕、
『中居正広という生き方』『社会は笑う・増補版』〔ともに青弓社〕など)
ドラマからバラエティーへ
「星に当たってしまった少年」。前回は、宮崎駿が語ったこの言葉に導かれながら話を進めた。
木村拓哉が主演したドラマに、「星」という言葉がタイトルに入った作品がひとつだけある。2002年にフジテレビ系で放送された『空から降る一億の星』である。『あすなろ白書』(フジテレビ系、1993年)、『ロングバケーション』(フジテレビ系、1996年)、『ビューティフルライフ』(TBS系、2000年)の北川悦吏子脚本による「月9」枠の恋愛サスペンスだ。
放送前から大きな話題になっていたのが、木村拓哉と明石家さんまの初共演だった。しかもさんまは「月9」自体、初の出演だった。とはいえ、俳優としての実績はすでにあった。1986年に主演し高視聴率を挙げた『男女7人夏物語』(TBSテレビ系)である。このドラマは、独身男女のもつれる恋愛模様を都会の風俗を交えて軽快に描き、「月9」の代名詞となったトレンディードラマの原点ともされる。その意味ではさんまに「月9」との縁がないわけではなかった。
そうしたなか始まったドラマでは、木村拓哉がフレンチレストランのコック見習い・片瀬涼、明石家さんまが刑事・堂島完三、深津絵里がその妹・堂島優子にそれぞれ扮し、殺人事件と3人の過去の秘密が絡みながら物語は展開していった。全話の平均視聴率が22.6パーセント、最終話がその年の連続ドラマで最高となる27.0パーセント(いずれも関東地区。ビデオリサーチ調べ)と数字的にも上々の結果を残した。
そしてこの共演がきっかけで木村拓哉と明石家さんまは交流を深め、2人による番組が企画される。2003年に始まり、いまや毎年正月恒例となっているバラエティー特番『さんタク』(フジテレビ系)である。
この番組、お互い未体験なことや苦手なことに挑戦するというのが一貫したコンセプトだ。何をするかを決めるトーク部分から始まり、実際に挑戦し、その余韻のなかでのエンディングでは木村拓哉がギターを手に弾き語りを披露するなど、正月番組ということもあって2人のリラックスした表情を見ることができる。
その際、未体験なものに挑むということから、お互い相手のフィールドへの挑戦が企画になることもある。2015年の放送では、さんまがSMAPのツアーのステージにサプライズ登場し、木村拓哉と「アミダばばあの唄」をデュエットした。
そして今年2016年の放送では、そのアンサー企画ということで木村拓哉が吉本の本拠地である劇場なんばグランド花月でさんまとともに人生初の舞台コントに挑むことになった。『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)でコント自体は数多くこなしているが、生の観客がいる舞台でのコントには、まったく違う緊張感があるのだろう。さんまと2人でアリクイに扮してのコントだったが、その緊張は終始見ている側にも伝わってきた。だが本番は初めてということを感じさせない出来栄えで、客席も大いに盛り上がるなかで無事終了した。
SMAPの他のメンバーがそれぞれレギュラーのバラエティー番組があるのに対し、現在木村拓哉個人にはない。しかし、ちょうど20周年を迎えた『SMAP×SMAP』などで見せてくれるコントやトークでの姿も彼を知るうえで忘れてはならないものだろう。そこで今回は、木村拓哉にとってのバラエティーとは何なのか、そしてそこに見て取れる彼ならではの魅力を探ってみたい。
録画再生能力
『空から降る一億の星』で木村拓哉が演じる片瀬涼には、物語のうえでも鍵となる特殊な能力がある。それは、どんなものでも一度見たら正確に記憶する能力である。例えば、ラックに並べられた数十のビデオパッケージのタイトルを一瞬見ただけで覚え、それが崩れてしまっても元の順番どおりに並べ直すことができる。
実は面白いことに、それと似たようなことを木村拓哉は自分自身についても語っている。それを彼は“録画再生能力”と呼ぶ。つまり、「映像を頭に焼き付けて、再現する」ことができるというわけである(木村拓哉『開放区』集英社、2003年)。
さんまは今年の『さんタク』のなかで「お前は覚えが早いから1日2時間だけ稽古すればいける」と言っていたが、この“録画再生能力”は、木村拓哉がさまざまな場面で私たちに感じさせてくれる勘のよさの秘密なのかもしれない。一つひとつ順を追って習得していくのではなく、全体を一気に把握することができる。例えば、彼の趣味のひとつであるサーフィンについてもそうだ。「波乗りに行く前は、プロのサーファーのビデオを見てから行く。自分が海に入ったときに、「ああやって、波に対して構えてたな」とか、「こうやってからだを傾けてたな」っていうのを思い出してやってみる」(同書)
当然それは、ドラマなどでも役に立つ能力だろう。実際、木村拓哉は、セリフを覚えるときには一度頭のなかでストーリーの流れを自分なりにビジュアル化したり、台本のページそのものを頭のなかに入れたりするという(同書)。
前回、木村拓哉にはプレーヤーとしての矜持があるということを書いた。彼にとって、プレーヤーであることは他のどのポジションにも代えがたい喜びである。この話もまた、そんなプレーヤー・木村拓哉の姿勢を示すものにちがいない。作家なり脚本家なりが作った世界観のなかに入り込み、そのなかで与えられた役柄を全うすること。そのことを楽しみ、また同時に自分に課している姿がうかがえる。
そしてその能力はおそらく、ドラマや映画だけでなく、バラエティーにも生かされているはずだ。
それを実感させる場面は、『さんタク』にもあった。コントの事前の打ち合わせのときのことだ。木村拓哉は、明石家さんまから共演する次長課長・河本準一の持ちギャグである『サザエさん』のマスオさんのセリフ「えぇーっ!?」の物真似をやるように言われた。突然言われて驚く木村拓哉。だが彼は、即座にそれを完璧にやってみせた。
振り返ってみても、『SMAP×SMAP』の初期の名作コントのひとつ「古畑拓三郎」などもそうだった。田村正和扮する古畑任三郎の物真似をする人は少なからずいるが、あそこまで“完コピ”できた例は、そうないだろう。あるいは、ドラマ『探偵物語』(日本テレビ系、1979―80年)の松田優作を真似た「探偵物語ZERO」の工藤や小室哲哉の独特のクネクネした動きを見事に再現したフラワーTKなども同様だ。
そこには、単なるパロディーというだけにはとどまらない、対象に没入し、同化してしまうような観察眼の鋭さが感じられる。だがそうしたことも、彼の“録画再生能力”のことを知れば十分納得できる。物真似をすることは、その意味では台本を覚えることと同じなのだ。
現場の人・木村拓哉
しかし、それをただコピー能力が高いというだけで片づけてはならないだろう。それは大前提としてあり、さらにそれ以上のものを見せてくれるところにプレーヤー・木村拓哉の本領はあると思えるからだ。
なんばグランド花月でのコントのときにも、そんな場面があった。朝5時のカラオケ屋という設定。疲れて寝ているさんまと河本、そして木村拓哉。ふと目覚めて「いま何時?」「女の子たち、もう帰った?」というフリのあとに木村拓哉が「うわっ、さっきの娘たちから、すごいライン来てる」とアドリブを発すると会場は爆笑に包まれた。
プレーヤーであるとは、現場の人であるということだ。人生初の舞台コントの緊張感のなか、木村拓哉は実際始まってみたら観客の反応をギャグにしたりするなど、ライブでの強さを随所に感じさせた。その象徴が、このアドリブだったといえるだろう。
ただ木村拓哉にとって現場とは、こうした観客がいるような場だけを指すのではない。
何度か裏話として語られていることだが、『SMAP×SMAP』のスタジオ収録の際、木村拓哉は待ち時間でも楽屋に戻らず、スタジオ前の控え場所である前室にずっといるという。そこもまた彼にとっては現場だからだ。「基本、出演者の役割は現場にいることだと思ってるから。本番だけが仕事じゃない。セット転換だったりコーナーが変わったりしているスタジオ内の動きを感じていたいし。メークさんや美術さんとちょっとコミュニケーションをとれるところにいたいってのもあるかな」(『SMAP×SMAP COMPLETE BOOK――月刊スマスマ新聞VOL.2~RED~』〔TOKYO NEWS MOOK〕、東京ニュース通信社、2012年)
ここでも、木村拓哉のプレーヤーとしての意識は一貫している。本番中だけでなく、収録の準備にスタッフが働いている場所もまた、彼にとっては現場である。「何を食うか、何をしゃべるか、何を歌うか。考えてくれるのもスタッフだし。スタッフがいて、初めて成り立っていることだから」(同書)
スタッフへの感謝の念も当然あるだろう。同時にこの言葉からは、セリフがすべて台本で決まっているわけではないバラエティーで、出演者、つまりプレーヤーとしてどのような立ち位置にあるかを彼が常に自覚していることがわかる。
そこからひとつ出てくる答えが、視聴者目線に立つということだ。「自分がスマスマの中で発する言葉とかって…なんか全然、業界目線じゃないんだよね(笑)。ホントに、視聴者の人を代表してしゃべってるような感じかな」(同書)
海外からの有名スターや普段ほとんどテレビに出ないようなアーティストが出演することも多い『SMAP×SMAP』で、木村拓哉が見せる反応は確かに驚くほど素直である。特に「やっべえ」とか「すっげえ」とかいった感嘆詞が発せられる頻度は、他のSMAPのメンバーよりもかなり多い印象だ。それはきっと、彼が「視聴者の人を代表」することをどこかでいつも意識しているからなのだろう。そしてそのことによって、テレビの前の私たちも彼らと同じ現場の人になることができるのだ。
下ネタの意味
バラエティーでのそうした姿からは、木村拓哉の「素」の部分も垣間見える。それは、「カッコいい」という言葉で括られがちな木村拓哉という存在の、違う人間的魅力を教えてくれる。
例えば、2014年のフジテレビ『FNS27時間テレビ』がそうだった。SMAPが総合司会を務めたこの年、深夜恒例の「さんま中居の今夜も眠れない」のコーナーに中継で登場した木村拓哉は、セクシー女優相手に“暴走”した。ハニートラップにかかり、痛い目に遭った経験をもつさんまのために安全なセクシー女優を紹介しようというコンセプト。そこで木村拓哉は居並ぶセクシー女優を相手に下ネタお構いなしで仕切り、むしろさんまや中居正広があわてて抑えようとしたくらいだった。
その中継が終了したCM明けのこと。「さんまさんに楽しんでもらうために身を削って頑張ってくれた」と中居がフォローすると、さんまは「身を削ってないよー、あいつ。あいつ、あんなんやで」と返す一幕もあった。
このさんまの言葉は、木村拓哉のラジオ番組『木村拓哉のWHAT’S UP SMAP!』(TOKYO FM)を聞いているファンであれば、大きく頷けるものだったかもしれない。
1995年に始まったこの番組では、彼の飾らない魅力が存分に楽しめる。その象徴が下ネタで、女性の下着の好みについて事細かに語ったり、自分の性の目覚めに絡んでボディコンブームの思い出を語ったりとほとんど定番化しているといってもいい。
そこから伝わってくるのは、彼の等身大的な少年の部分だ。聞いているのは同性ばかりではなく、むしろ当然女性のほうが多いだろう。しかし、そこには思春期の少年が同年代の友人同士で交わす下ネタのノリが感じられる。『27時間テレビ』の“暴走”も、そうしたかわいげを感じさせる部分があったからこそ笑いに昇華できたのだろう。
このラジオの仕事で木村拓哉と知り合った放送作家・鈴木おさむは、同じ1972年生まれの同級生、まさに同年代の友人だ。そんな鈴木おさむとの何げない会話のなかから生まれたコントが、『SMAP×SMAP』の人気キャラクター「ペットのPちゃん」である。「移動で飛行機に乗ってる間、おさむとずっと「こういうやつが、こんなことして、こんなこと言ったら、面白くない?」と話していって。(略)ピンクの犬の着ぐるみを着てるやつなんかも、飛行機のなかでずっと話して作ったもののひとつだよね」(「Bananavi!」vol.001、日本工業新聞社、2014年)
Pちゃんのコントも、ご存じのように下ネタのノリがベースにある。このキャラクター、木村拓哉扮する犬のPちゃんが飼い主である稲垣吾郎扮するパパの目を盗んでママや遊びにきた女性ゲストに突然人間の言葉を話し、誘惑し始める。
こうした下ネタは『SMAP×SMAP』には珍しく、当初はコーナー前に「大人の方のみご覧頂けます」とのクレジットも出ていたほどだ。最近では主婦の不倫を描いて話題になったドラマ『昼顔――平日午後3時の恋人たち』(フジテレビ系、2014年)のパロディーコント「昼顔」もあるが、「ペットのPちゃん」は番組開始直後の1996年5月から始まっている。となると、下ネタはやはり、年齢に合わせた題材の変化というよりは、木村拓哉の「素」の部分からくるものであることがうかがえる。
色気のありか
また木村拓哉は、自分でも認めるように「エロい」という表現をよく使う。しかしこの場合は、単なる下ネタとは違って、人がもつ色気を木村拓哉流に表現したものだ。年齢に関係なく、「向こうに何があるのか見たかったら、多少の塀ならよじのぼっちゃうような感じ」(木村拓哉『開放区2』集英社、2011年)と木村拓哉はそれを例える。いかにも冒険心あふれる彼らしい表現だ。
そしてそういう人に多く出会えるのは、仕事の現場だという。「それぞれのパートで、それぞれ担っている責任を、個性を駆使して果たしている。おもしろいボキャブラリーを持っているし、引き出しも多い。名刺なんて必要なくつき合える」。つまり、「根っこの部分の人間的魅力」があってこその色気なのだ(同書)。
ではそんな色気はどうすれば醸し出せるのか? 木村拓哉はこう答える。「それは自分の足で動いて、いろんなものを見て、たくさん感じること。たぶんライブの動きひとつにしても、憧れたアーティストのステージングを見たからこそ生まれるものだろうし、被写体になるときも、好きな写真集を見てなかったらできない表情をしてるかもしれない」(同書)
“録画再生能力”は、こんなところにも発揮されているといえるだろう。ライブのステージングやカメラの被写体になるときの表情。当然ドラマや映画でひとつの役柄を演じるときもそうだろう。そしてコントでも。
そう言われると、木村拓哉のコントキャラクターは一様にどこか「エロい」。パラパラブームに一役買ったバッキー木村や「ホストマンブルース」のホスト・ヒカルのような設定からしてそのようなキャラクターはもちろんだが、「スマスマ高校メガネ部っ!」のキャプテンのような、瓶底メガネに奇妙なカツラという扮装をした、気弱そうなキャラクターでもそうだ。このキャプテンのイメージは、木村拓哉が描いたスケッチがもとになっているという(『SMAP×SMAP COMPLETE BOOK――月刊スマスマ新聞VOL.3~BLUE~』〔TOKYO NEWS MOOK〕、東京ニュース通信社、2012年)。その点、ここでも彼の記憶の蓄積、“録画再生能力”が一役買っているのだろう。
またあでやかさという意味では、いくつかの女性・女装キャラも思い浮かぶ。「竹の塚歌劇団」の愛ゆうき、「ギャル店員シノブ」のシノブなど、性別を超えて「きれい」という表現がぴたりとはまる。2005年の『さんタク』では、ビヨンセのプロモーションビデオを再現するという企画で自らビヨンセに扮し、さんまやスタッフをざわつかせる場面があったことも思い出す。
なるほど、こうしたキャラクターが残すインパクトは、彼がもつビジュアルの力があってのものだろう。ただ、コントの基本はキャラクターを演じきることだ。「ちょっと1回タンマ」など若者には意味不明な言葉を使ってしまい、46歳という本当の年齢がばれそうになるが、息子の高校受験の費用が必要なために必死に取り繕うシノブなど、おかしくはあるが「根っこの部分の人間的魅力」にあふれている。だからこそ、木村拓哉が演じるキャラクターはどれも、鮮やかでオリジナルな印象を私たちに残すのではないだろうか。
偶然の一致
SMAPがデビュー当時、歌番組の減少もあってなかなか軌道に乗れずバラエティーに活路を求めたことは、いまや知る人ぞ知るところだろう。それは、アイドルが本格的バラエティーに取り組むことなど、まだ前例がない時代のことだった。
当初、木村拓哉のなかでは、バラエティーに出ることは「人に笑われる」という感覚が抜けきれず、抵抗が強かったという。だがお笑い芸人たちとの出会いが、彼を変える。「すごい努力だったり、すごい感覚だったりがないと、人を笑わせることはできない」(前掲「Bananavi!」vol.001)、そう考えるようになったのである。
それは、「一番最初に密接に知り合ったのが、いきなりさんまさんだったから、なおさら強く感じ」たことでもあった(同誌)。その意味で、「叔父貴」と呼んで慕うさんまとの『さんタク』でのコント共演は、「いままでかいたことのない汗をかいた」とコント後に振り返った木村拓哉にとって、記念すべき一ページになったにちがいない。
そして木村拓哉は、「“人を泣かせる”ということと、“人を笑わせる”っていうことは同じなんだな」といつしか思うようになった(同誌)。つまり、ドラマとバラエティーは、本質的に変わらない。
『空から降る一億の星』で木村拓哉扮する片瀬涼は、幼いころに父親を失った出来事がきっかけで施設に育ち、人を愛することができないでいる。父親の死の場面も、そのとき受けたショックがもとで思い出せない。だが、明石家さんまと深津絵里扮する兄弟と運命の糸が絡み合うなかで、あるとき彼は“録画再生能力”を取り戻し、父親の死の場面をまざまざと思い出す。しかしそのことによって物語は悲劇的な結末へと向かっていく。
その結末を迎える直前の場面、木村拓哉が見せる演技が強く印象に残る。深津絵里扮する堂島優子との出会いによって人を愛することを初めて知った片瀬涼は、それまで見せていた冷酷なまでにクールな表情とは一変し、最後の最後に涙ぐみながら優しく彼女にほほ笑む。その泣き笑いの表情が、美しくも哀しい。
それは、このドラマの主題歌であるエルビス・コステロの「スマイル」が歌う歌詞を思い出させる。「ほほ笑んで 心が痛くても ほほ笑んで 心が折れそうになっても」と歌いだすこの歌もまた、喜びが悲しみや苦しみと背中合わせのものであり、でもだからこそほほ笑もうとささやきかける。ドラマのラスト、一人残された明石家さんま扮する堂島完三が、涼と優子の2人が残していったカセットテープから流れる「見上げてごらん夜の星を」を聞き号泣したあと、何かを吹っ切るようにほほ笑むシーンも、そのことを暗示する。
「スマイル」は、もともと映画音楽として作られた。作曲したのは喜劇王と呼ばれるチャールズ・チャップリン。自らが主演した映画『モダン・タイムズ』(1936年)で使われた曲である。その後歌詞付きのバージョンができ、多くのアーティストによってカバーされてきた。エルビス・コステロもそのひとりだ。
そしてチャップリンを尊敬する人に挙げるのが、中居正広である。SMAPが結成されてまだ間もないころ、チャップリンの『街の灯』(1931年)を観て感動した中居正広は、チャップリンの伝記のなかで「喜怒哀楽の中でいちばん難しいのは、人を喜ばせること、笑わせることだ」という一文に出合い、バラエティーの道を究めようと決意する(「中居くん日和」「ザテレビジョン」1997年8月29日号、角川書店)。
バラエティーに真摯に取り組むなかで木村拓哉が得た「“人を泣かせる”ということと、“人を笑わせる”っていうことは同じなんだな」という思い。それは、中居正広が出合い、彼を動かしたチャップリンの言葉と確かに響き合っている。こうして2人は、それぞれ別の道筋をたどりながらも、同じ場所に行き着いたのだ。その偶然の一致に、私はSMAPというグループが作り上げるエンターテインメントの本質、そして深さを垣間見た思いがした。
Copyright Shoichi Ota
本ウェブサイトの全部あるいは一部を引用するさいは著作権法に基づいて出典(URL)を明記してください。
商業用に無断でコピー・利用・流用することは禁止します。商業用に利用する場合は、著作権者と青弓社の許諾が必要です。